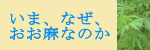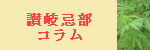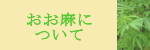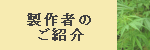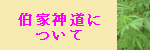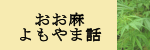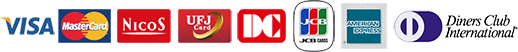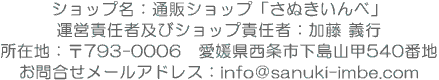|
おお麻(ヘンプ)とは、世界各地に分布するアサ科の一年草のことです。日本では、「大麻草」、あるいは「大麻」と呼ばれる植物をいい、亜麻やマニラ麻など世界で20種類以上ある麻のうちの一種です。
■おお麻、ヘンプという用語-----当店では“おお麻”で統一しています。法律や日本の伝統文化との関係などで、わかりづらい場合は大麻と表現しています。
■日本国内での個人使用-----おお麻を嗜好品(ドラッグ)としては推奨していません。大麻取締法では所持・栽培・譲渡等が禁じられています。
■当店の立場-----おお麻は経済・文化・地球環境といった面で利用価値の高い植物であり、循環型社会の形成に必要なバイオマス(生物資源)のひとつと捉えています。
1.日本の法律上の位置づけ
大麻草というと、誤解されがちなのですが、大麻取締法という法律上、大麻とは花穂と葉のことで、種子と茎、これらからできた製品は対象外です。
大麻取締法 第1条〔大麻の定義〕
| この法律で「大麻」とは、大麻草(カンナビス・サティバ・エル)及びその製品をいう。 ただし、大麻草の成熟した茎及びその製品(樹脂を除く。)並びに大麻草の種子及びその製品を除く。 |
日本の大麻取締法上の大麻草の位置づけ
|
合法(法規制外部位) |
違法(法規制部位) |
| 大麻草 |
成熟した茎と種子 |
大麻=花穂と葉 |
| 大麻草からできる製品 |
伝統工芸利用
麻織物・神事用・民芸品・花火・弓弦・結納品など |
医療利用
鎮痛剤・制吐薬・緑内障薬
神経性難病薬 |
産業利用
衣服・雑貨・紙・食品
建材・化粧品・燃料など |
嗜好品
ソフトドラッグとしてマリファナ・ハッシッシなど |
※大麻草の栽培は、都道府県知事の許可を得なければならない。
「ヘンプ読本」築地書館より。
2.おお麻の歴史と他の繊維との違い
調べてみると、おお麻(ヘンプ)は、日本においては戦前まで衣食住をはじめ、医療、建築、神事などに日本の文化と歴史に深く関わりながら、絹とともに綿よりもずっと古くから使われてきたようです。
主な繊維材料との違いを表にまとめてみました。
主な繊維材料の種類
| 種類 |
大麻草 |
絹 |
綿 |
| 呼び名 |
たいまそう |
きぬ |
めん |
| 別名 |
Hemp
ヘンプ |
Silk
シルク |
Cotton
コットン |
| 学名 |
Cannabis Sativa L.
カンナビス・サティバ・エル |
- |
Gossypium.
ゴシピウム |
| 分類 |
アサ科
一年草 |
- |
アオイ科ワタ属
多年草 |
| 原産地 |
中央アジア |
中国 |
インド
アフリカ |
| 世界の主な生産国 |
中国
フランス
ルーマニア |
中国
インド
タイ
日本 |
世界60カ国以上 |
| 遺跡等での出土 |
中国・ゴビ砂漠の墓遺跡から2700年前の乾燥大麻 |
紀元前1000年頃の古代エジプト遺跡から中国絹の断片 |
紀元前2500年頃から古代インダス地方で繊維作物として栽培 |
| 日本への伝来時期 |
福井県・鳥浜遺跡(1万年前)から種子と繊維 |
弥生時代前期の墓から出土 |
平安時代初期 |
| 日本の産地 |
栃木
長野 |
群馬
埼玉
福島 |
大阪
静岡
愛知
兵庫 |
| 主な用途 |
下駄の鼻緒、蚊帳、衣料、混紡地、畳の縦糸 |
衣料、寝具、弦楽器の弦 |
衣料、寝具 |
| 特徴 |
・強い
・放熱性が高い
・汗を蒸発させる効果がある
・抗菌作用がある
・消臭力がある
・従来の麻製品(亜麻や苧麻)にはない、やわらかな肌触りと風合い |
・軽くて丈夫、やわらかい
・吸湿性が良い
・染色性が良い
・通気性が良い
・家庭での洗濯が困難
・変色しやすい
・虫に食われやすい |
・伸びにくい
・丈夫
・吸湿性がある
・肌触りがよい
・縮みやすい |
「ヘンプ読本」築地書館などを参考に作成。
普段の私たちの生活で最も用いられているのは綿(コットン)ですが、栽培時に大量の除草剤、殺虫剤等の農薬が使われており、製品化の工程でも多くの化学薬品が使われていることはあまり知られていません。
農薬を使わずに栽培するオーガニックコットンと並んで、自然派志向の定番となってきたのがおお麻(ヘンプ)です。
とくに近年、おお麻(ヘンプ)は約90日で3~4mにも成長する生産性の高さや、さまざまな製品に活用できる応用性から、日本以外の国、ヨーロッパやカナダなどの欧米諸国では環境素材として見直され、石油に変わる循環可能な社会形成に不可欠な植物として注目されています。
3.これまでの麻と、おお麻の違い
戦前までは麻といえば、おお麻(ヘンプ)のことだったようです。それが戦後60年以上を経て認識が違うものになりました。
現在は麻と言えば、亜麻(あま、リネン)と苧麻(ちょま、ラミー)を指します。
なお、家庭用品品質表示法で、麻と表示することが認められているのは、衣服やシーツの素材として使われている亜麻と苧麻の2種類だけで、おお麻(ヘンプ)は“指定外繊維”として扱われます。
従来の麻、亜麻と苧麻
| 種類 |
亜麻 |
苧麻 |
| 呼び名 |
あま |
ちょま |
| 別名 |
Flax
フラックス
リネン |
Ramie
ラミー
からむし |
| 学名 |
Linum usitatissimum. |
Boehmeria nivea Gand. |
| 分類 |
アマ科
一年草
|
イラクサ科
多年草 |
| 原産地 |
中央アジア |
東南アジア |
| 世界の主な生産国 |
中国北部
フランス
ベラルーシ |
中国南部
ブラジル
フィリピン |
| 遺跡等での出土 |
紀元前3000~4000年頃のスイス遺跡から種と繊維で織った布 |
中国・新石器時代の遺跡から4700年以前の布と紐が出土 |
| 日本への伝来時期 |
明治初期 |
秋田県・中山遺跡(縄文晩期)から編布 |
| 日本の産地 |
北海道 |
本州各地
福島 |
| 主な用途 |
服、帆布、漁網、ホース、芯地 |
服、寝装具、資材、漁網、芯地 |
| 特徴 |
・繊維は細く短い
・糸強力はラミーに次ぐ
・色はリネン特有の黄味がかった色
・シャリ感が少なくしなやかである
・水分の吸収、発散性がラミーに次ぐ |
・繊維は太く長い
・糸強力は強い
・色は白く、絹のような光沢がある
・シャリ感があり腰がある
・水分の吸収、放湿、発散性に優れている |
「ヘンプ読本」築地書館などを参考に作成。
おお麻(ヘンプ)は、従来の麻には無い柔らかな肌触りと風合いが特長です。
下記に、おお麻(ヘンプ)の特長をまとめました。
・熱を逃がし、汗をすぐ乾かせ、また清涼感があります。
・繊維の細長い空洞(ルーメン)をもつ内部構造によって、静電気がおこりにくいです。
・サラサラとした風合いとシャリ感で暑い夏は涼しく、寒い冬も肌を快適に保つことができます。
・腰としなやかさ、独特の質感とツヤ、ナチュラル感のある風合いを併せ持っています。
4.世界の産業用おお麻(ヘンプ)
おお麻の日本における栽培面積はここ5年、約6ヘクタールと横ばいで推移していますが、世界を見渡すと、「産業用ヘンプ」は、医療用・嗜好用と分別され、先進国を中心に生産・利用の両面で急速な発展を遂げているようです。
たとえば、アメリカの産業用ヘンプの市場規模は2016年で6億8800万ドル(約778億円)(http://urx.mobi/DOOZ参照)におよびます。
おお麻の用途別の種類
| 名称 |
品種 |
主な
利用部位 |
利用目的 |
定義 |
Industrial hemp
産業用ヘンプ |
繊維型 |
種子、茎、葉 |
産業用 |
THC濃度0.3%以下の品種
CBD濃度は1 ~3% |
Medical marijuana
医療用大麻 |
薬用型 |
花序、葉 |
治療 |
THC濃度5 ~20%の品種 |
Recreational use
嗜好用大麻
マリファナ |
花序 |
嗜好品 |
THC濃度5 ~25%の品種
対象年齢は21歳以上
タバコ代替の課税対象 |
『農業経営者』2017年10月号, P.16より引用。
産業用ヘンプは、茎、種子、葉の3つの生産物からさまざまな加工を経て、各種商品がつくられます。それぞれの部位にはさまざまな利用用途があり、新しい分野での用途開発が進められている状況です。
産業用ヘンプの事業領域
靭皮繊維
1.5 ~ 2.5トン/ヘクタール |
オガラ(麻幹)
5 ~ 10トン/ヘクタール |
麻の実
0.7 ~ 1.5トン/ヘクタール |
麻の葉
1 ~ 2トン/ヘクタール |
<紡績>
麻布・衣類、ロープ・紐、靴、アクセサリー、ふとん
<不織布>
断熱材、床マット、植生マット緩衝マット、自動車部品
<成形加工>
自動車内装材、FRP強化材
<パルプ>
タバコ巻紙、印刷用紙、絶縁紙 |
<チップ化>
馬・牛敷藁、小動物用敷藁、左官材料、壁材、園芸資材
<微粉砕>
プラスチックの副原料、堆肥
<合板>
住宅建材、家具、インテリア
<炭化>
火薬原料、調湿材、土壌改良材、水質浄化材、カーボンナノチューブ
<パルプ化>
特殊紙、レーヨン原料 |
<食品>
七味唐辛子、和え物、菓子、麻ミルク、パン、パスタ・そば、ビール、バター、ドレッシング、料理油、サプリメント、プロテインパウダー
<生薬>
麻子仁(マシニン)
<オイル>
木工塗料、化粧オイル、潤滑油、石けん
<飼料>
鳥用・魚用エサ、家畜飼料 |
<畑に還元>
肥料
<乾燥・粉砕>
食品原料、ハーブ茶
<抽出>
CBD製品(サプリメント、チンキ剤、菓子、飲料、電子タバコ、クリーム等の化粧品、ペット用食品)、医薬品原料 |
※THC濃度0.3%未満の産業用ヘンプの品種であっても製品化が違法な国・地域がある。
『農業経営者』2017年10月号, P.19より引用。
5.大麻取締法のおもな改正点
2023年の秋の臨時国会において、75年ぶりに大麻取締法改正案が可決、成立、12月13日付の官報にて公布されました。どのように法律が変わったかは下記にまとめられています。
。
大麻取締法のおもな改正点
| 項目 |
現行法
|
改正法 |
| 法律名
|
「大麻取締法」(1948年に制定)
|
「大麻草の栽培の規制に関する法律」(2025年に施行予定)
※略称:大麻草栽培法 |
| 法律の目的
|
目的規定なし
|
「大麻草の栽培の適正を図るために必要な規制を行うことにより、麻向法と相まって、大麻の乱用による保健衛生上の危害を防止し、もって公共の福祉に寄与すること」 |
| 規制の対象
|
大麻草の植物部位による
【×規制対象】
花穂、葉・未成熟の茎、成熟した茎から分離した樹脂、根
【○規制対象外】
成熟した茎(樹脂除く)、種子
|
【×麻向法の「麻葉」に指定】
「大麻、△9-THC、△8-THC、化学的変化により容易に麻薬に生成するもの(例:THCA)」を麻薬に指定
【○規制対象外】
「成熟した茎、種子、政令で定める基準値を超えない大麻草の形状を有しない製品」 |
| 栽培の目的
|
神事や伝統的な利用に限定
(ただし、運用上、新規栽培は禁止)
|
医療および産業の分野への利用
例:大麻由来医薬品、国産のCBD製品、バイオプラスチック、建材、ヘンプ食品など |
| 免許の種類
|
【都道府県知事の免許】
大麻栽培者、大麻研究者
|
【都道府県知事の免許】
第一種大麻草採取栽培者(一般製品原料)
【厚生労働大臣の免許】
第二種大麻草採取栽培者(医薬品原料)
大麻草研究栽培者 |
| 栽培地の用件
|
都道府県で対応が異なる
(THC濃度に関係なく、高いフェンスで囲む、監視カメラの設置など厳しい防犯体制が求められた)
|
全国的な統一基準を設ける
THC濃度が基準値以下の大麻草には、特に厳しい防犯体制を求めない
THC濃度が基準値を超える大麻草は厳格な管理下での栽培が可能 |
|
免許期間
|
1年
(対象年の12月31日まで) |
第一種大麻草採取栽培者:3年
第二種大麻草採取栽培者:1年
大麻草研究栽培者:1年 |
| 種子の扱い
|
【播種用】
海外品種の輸入は禁止
種子譲渡は原則禁止
【食用/飼料用】
発芽不能処理をすること
(経産省:貿易管理令輸入公表)
|
【播種用】
海外品種は第一種大麻草採取栽培者が輸入可
第一種大麻草採取栽培者間の譲渡可
【食用/飼料用】
国内生産、全国流通のいずれも可能。ただし、発芽不能処理をすること |
| 花葉の加工 |
全面禁止
|
第一種大麻草採取栽培者が厚生労働大臣の許可を得れば、自社加工&委託加工が可能 |
| CBD製品
|
THC濃度の基準値なし
|
THCの残留限度値を設定(別途政令で定める)
THC検査体制を整備(登録検査機関、未定)
CBD医薬品として承認後に食薬区分の対象に(未定)
CBD化粧品は、ポジティブリストの対象に(未定) |
| 付帯事項
|
|
施行後5年を目途として、施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、必要な措置を講ずるものとする |
『農業経営者』2024年1月号, P.39より引用、一部編集。
注:麻向法=麻薬及び向精神薬取締法
参考:大麻草の栽培の規制に関する法律案、麻薬及び向精神薬取締法を一部改正する法律案
|